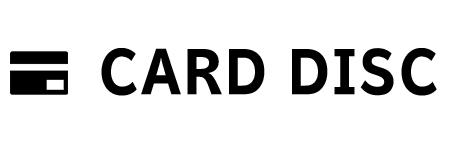デジタル証券がSBI・三菱UFJなどから3億円調達──国内STO拡大の起爆剤となるか

資金調達の概要
シリーズAセカンドクローズとは何か
デジタル証券株式会社は2025年9月25日、シリーズAラウンドのセカンドクローズとして総額3億円を調達したと発表しました。調達先はSBIグループの投資ビークルであるSBI Ventures Three、三菱商事、そして三菱UFJ銀行と三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合です。本ラウンドにより同社の累計調達額は12億円へ到達し、資本面でプラットフォーム拡張の土台が一段と強化されました。発表は公式プレスリリースで確認できます(PR TIMES)。
セカンドクローズは、同一ラウンド内で条件を変えず追加出資を募る手法です。今回3億円という追加調達は、サービス開始前後に必要な開発費やライセンス取得費用の目途が立ったこと、そして新規投資家を迎えることで経営資源の多角化を図る狙いがあります。ブロックチェーン関連スタートアップでは、需要が読みにくい市場を踏まえ小刻みに資本注入を行うことで資本効率を高めるケースが増えています。
主要出資者の狙いとシナジー
出資各社の役割整理
今回参加した4社(組合)は、単なる資金提供にとどまらず、今後の事業展開に密接に関与するステークホルダーです。各社の狙いを整理すると次のとおりです。
- SBI Ventures Three:持株会社SBIホールディングスはデジタルアセット事業を拡大中で、自社グループの証券・銀行・暗号資産サービスとAPI連携できるパートナーを求めています。
- 三菱商事:総合商社として不動産・再エネなど実物資産のデジタル化を推進しており、トークナイズによる資産流動性向上に期待。
- 三菱UFJ銀行:メガバンクとしてST(セキュリティ・トークン)の決済・カストディ体制を構築中。投資はサービス連携を見据えた布石。
- 三菱UFJキャピタル:MUFGグループのCVC。フィナンシャル・イノベーション領域を重点投資分野と位置付け、成長企業支援でリターンと業務提携効果を両取りする狙い。
金融・商社の強力な株主を得たことで、デジタル証券社は発行体ネットワーク拡大に欠かせない「資産の目利き」「投資家基盤」「決済インフラ」の3点を一気に補完できる体制となりました。出資各社の詳細はプレスリリースおよび三菱UFJキャピタルの発表資料から確認できます(PR TIMES)。
デジタル証券社のビジネスモデル
「renga」プラットフォームの特徴
同社はブロックチェーン上で実物資産を裏付けとするファンドをトークン化し、1口10万円から販売できるオンラインマーケットプレイス「renga」を運営しています。口座開設は2025年9月1日に始まり、個人投資家がスマートフォンだけでSTO(Security Token Offering)に参加できる仕組みが整いました。背景には金融商品取引法改正で個人向けSTの小口販売上限が緩和されたことがあります(CoinDesk JAPAN)。
収益源は①初回発行手数料、②二次流通時のマッチング手数料、③発行体向けSaaS利用料の3本柱です。フロービジネスとストックビジネスを併せ持つ点が特徴で、投資家への透明なコスト提示と、発行体への運用効率改善を両立しています。ブロックチェーン基盤にはイーサリアム互換の独自サイドチェーンを採用し、ガス代の変動を吸収する設計です。
国内STO市場の現状と課題
規模拡大フェーズへ移行
日本のSTO市場は、2019年に大手証券5社が自主規制団体「日本STO協会」を設立して以降、証券会社主導の案件が中心でした。しかし2023年の金融商品取引法改正で「発行総額10億円未満」の小規模公募ST制度が創設され、ベンチャー主体のSTO事例が増加。2025年上期の公募ST発行総額は約145億円(STO協会集計)と前年同期比1.8倍へ拡大しました。
課題は①投資家保護ルールの複雑さ、②カストディや決済の法的位置づけ、③二次流通市場の流動性不足の3点です。今回の資金調達により、デジタル証券社はパートナー金融機関と連携し、カストディと決済領域で業界基準を整備する構えを示しています。制度整備とユースケースの拡大が同時並行で進むことで、市場は本格的な成長局面に入るとみられます。
SBI・MUFG連合がもたらすインパクト
国内メガプレイヤー連携の意味
暗号資産事業者として攻めの姿勢を見せるSBIと、伝統的金融の雄であるMUFGグループが揃ってスタートアップへ出資する事例は珍しくありませんが、証券トークン特化の企業を共同支援する形は注目に値します。大手が協調することで、技術標準やリスク管理体制が統一され、「島宇宙化」しがちなデジタルアセット市場に総合的なエコシステムが生まれる可能性があります。
特にメガバンクは中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証にも関わる決済インフラを研究中で、ST決済を兼用できるハイブリッドプラットフォーム構想を公言しています。その布石としてデジタル証券社のテックスタックを検証し、将来的な組込み型金融(Embedded Finance)サービスへの応用を狙うとみられます。
今後の注目ポイント
短期と中長期のマイルストーン
同社が示す公開マイルストーンは以下のとおりです。
- 2025年度内:第一号公募型デジタル証券ファンドの販売開始(目標発行総額5億円)。
- 2026年:第二次流通市場機能の正式ローンチと個人間売買の解禁。
- 2027年:累計流通総額1000億円、会員数15万人の達成。
調達資金はシステム開発と人材採用に6割、残りをマーケティングとガバナンス強化に充てる計画です。資金使途にガバナンス費用を明示するのは、金融庁がSTOの内部管理態勢を厳格化している現状を踏まえたものです。引き続き、発行スキームや投資家勧誘プロセスが金融商品取引法の枠組みに適合するかが最大の焦点となります。
石井英治
資金調達アドバイザーとして企業・個人の資金繰りのサポートを行う。モットーは「資金調達は安全で信頼できるサービスを選べ」。業界歴25年。