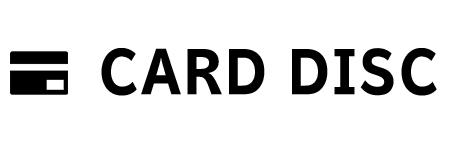ダルトン、9月30日付で資本金を1億円へ無償減資――イトーキグループの資本政策と成長戦略を読み解く

ダルトンが9月30日に減資を実施――臨時株主総会決議から効力発生日まで
研究施設や半導体製造装置などの開発・施工を行う株式会社ダルトン(東京都中央区築地、代表取締役社長:澤田正)は、2025年9月30日を効力発生日として資本金を1億円へ減少させる「無償減資」を実施しました。本件は2025年7月28日に開催された臨時株主総会で可決され、公式発表(2025年9月24日付)で詳細が公表されています。減資後も発行済株式総数に変更はなく、現金払戻しも伴わないため、一般株主の保有株式数や議決権比率には直接的な影響はありません。
近年、国内製造業では制度改正を利用して自己資本の最適化を図る動きが活発化しています。ダルトンはイトーキグループの一員として研究施設・教育施設・クリーン機器といった多角的事業を展開しており、今回の措置は「事業規模に見合った適正な資本金額」と「資本政策の柔軟性」を確保することを狙いとしています。
減資の具体的内容――1,387,182,500円から100,000,000円へ
減資のスキームは、会社法第447条に基づく「無償減資」であり、減少額は1,287,182,500円です。以下のように資本金勘定を組み替え、その他資本剰余金へ振り替えました。
- 減資前資本金:1,387,182,500円
- 減資額:1,287,182,500円
- 減資後資本金:100,000,000円
- 払戻し:なし(無償減資)
- 発行済株式総数:変更なし
資本金の一部を資本剰余金へ振り替えることにより、債権者保護手続を経ずに自己資本内での科目変更を可能としました。これにより同社は将来の事業投資やグループ内再編に備えた資本機動性を高めています。詳しくはダルトン公式リリースを参照してください。
減資の目的――資本政策の柔軟性と財務健全性の両立
ダルトンは研究施設や粉体機械など設備産業向けの大型案件を多く抱え、案件規模に応じて在庫・与信・保証債務が大きく変動します。そのため、過度な資本金を維持すると配当可能限度額が圧縮されるほか、自己資本利益率(ROE)が低下しやすい構造でした。今回の減資により、その他資本剰余金が増加し、今後の配当政策や自己株式取得など多面的な資本施策を検討できる余地が広がります。
同社は公告で「イトーキグループの一員として、更なる成長性戦略を推進する」旨を示しています。親会社の株式会社イトーキはオフィス家具・設備で培った営業ネットワークを活用し、ダルトンのラボ建設事業や半導体装置事業とのシナジー拡大を図っています。今回の減資は、グループ横断での資金再配分やM&Aを含むポートフォリオ強化を見据えた布石といえます。
イトーキグループ内での位置づけとシナジー効果
イトーキグループは「働く環境」「知の創造環境」を両輪に事業を展開しています。ダルトンはその中で研究施設・教育施設・クリーン機器・半導体装置の設計・施工を担い、グループ売上高約2,100億円のうち1,900億円を占めるワークプレイス事業と補完関係にあります。
グループ全体では、オフィス・ラボ・クリーンルームといった横串の提案強化を進めており、ダルトンが保持するラボ設計ノウハウとイトーキが強みとするオフィス什器のデザイン力を融合させ、研究者の創造性を高める環境構築を提案しています。減資で得た柔軟な資本構成は、こうした統合提案を推進するための設備投資や販促活動に活用される見通しです。
無償減資の手続と株主への影響
無償減資の場合、株券枚数や議決権比率が変動しないため、一般株主は資本上の希薄化や払戻し課税リスクを負いません。また、本件では債権者保護手続を省略できる範囲で行われており、公告期間や異議申述期間の設定は不要でした。
一方で、純資産の部内で資本金が減少し資本剰余金が増加するため、連結・単体いずれの貸借対照表でも自己資本合計に変動はありません。配当余力や自己株式取得原資として利用可能な「その他資本剰余金」が増えることで、株主還元方針に変化が生じる可能性があります。取締役会は今後の市場環境を踏まえ、最適な株主還元策を検討するとしています。
事業概要と沿革――創業86年のラボソリューション企業
ダルトンは1939年創業の老舗企業で、ドラフトチャンバーに端を発する理化学機器技術をコアに事業を拡大してきました。現在は研究施設事業、教育施設事業、粉体機械事業、クリーン機器事業、半導体装置事業の5本柱で構成されており、グループ会社を含む総従業員数は361名(2024年9月末時点)です。資本金減少前の財務指標では、2024年度売上高は195億円、営業利益は12億円を計上しました。
近年は半導体関連需要の高まりを受け、ウエハ洗浄装置や乾燥装置など前工程向け装置の開発・販売を強化。これら新規投資は減資とは独立して継続される方針であり、「資本効率を意識しながらも成長投資は維持する」と会社側は説明しています。会社概要はコーポレートサイトで公開されています。
財務指標への影響――ROE向上と配当適正化
資本金を減らすことでB/S(貸借対照表)の総資本がスリム化し、分母が小さくなる関係で自己資本利益率(ROE)は理論上上昇します。例えば、2024年度実績に同じ利益水準を当てはめると、ROEは減資前の約8%から約10%台に上昇すると試算されます。これは資本コストを意識する海外機関投資家にとってポジティブな要素となります。
一方、自己資本比率や流動比率など安全性指標にはほぼ影響がありません。資本金の減少は「資本勘定の振替」にとどまり、総資産・純資産は変わらないためです。同社は引き続き健全な財務体質を維持しつつ、剰余金の範囲内で安定配当と機動的な自己株買いの両立を目指すとしています。
今後のスケジュールと留意点――経過措置の終了後も情報開示を継続
今回の減資は2025年9月30日に法的効力が生じ、経理上も同日付で処理が完了しました。ただし、登記完了確認や税務署への届出など実務的な手続きは10月上旬まで継続します。決算公告や有価証券報告書などの法定開示書類には、減資後の資本金額が反映される予定です。
投資家や取引金融機関は、2025年11月発行見込みの第85期(2024年10月~2025年9月)決算短信・有報を確認することで本件の定量的インパクトを把握できます。ダルトンは公式ウェブサイトで随時情報を更新するとしており、株主・ステークホルダーは引き続き開示動向を注視することが推奨されます。
石井英治
資金調達アドバイザーとして企業・個人の資金繰りのサポートを行う。モットーは「資金調達は安全で信頼できるサービスを選べ」。業界歴25年。